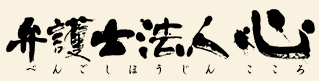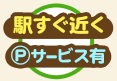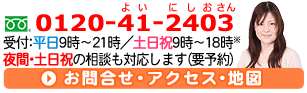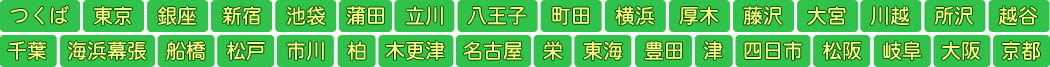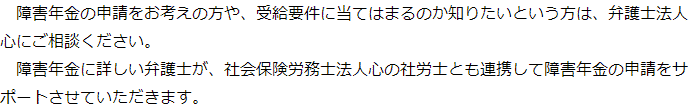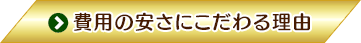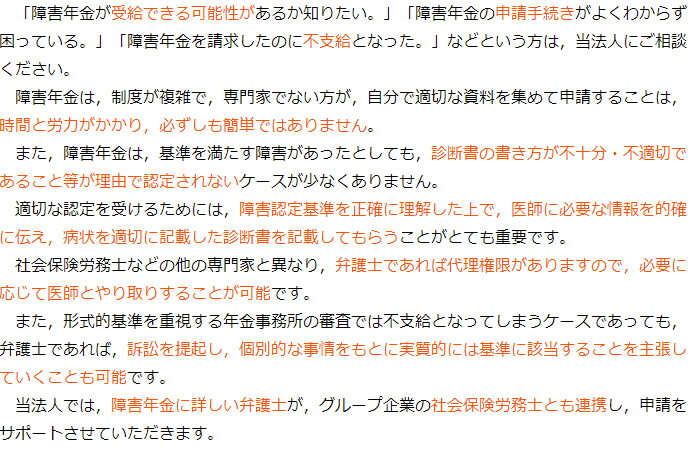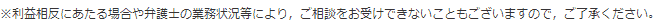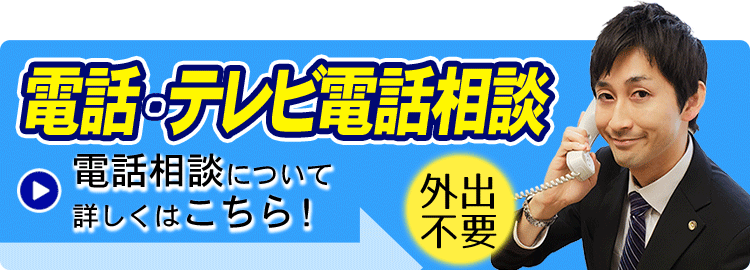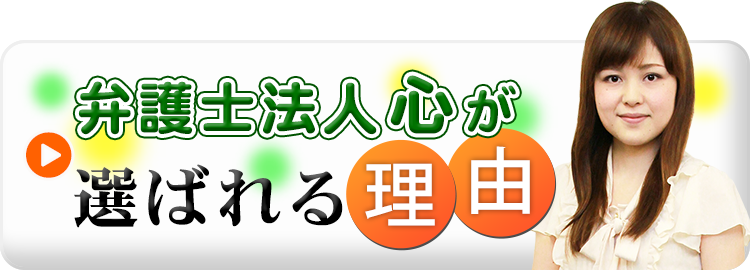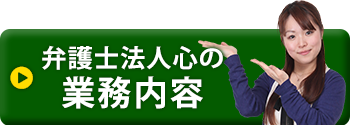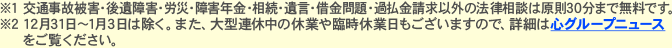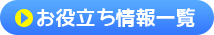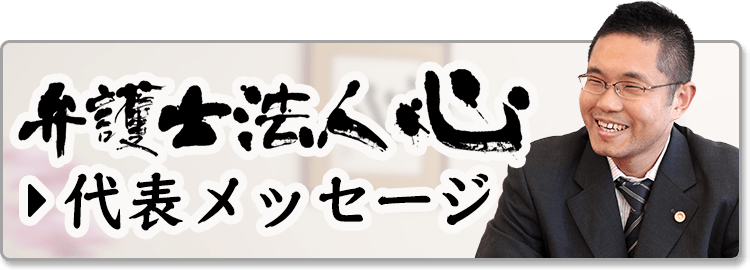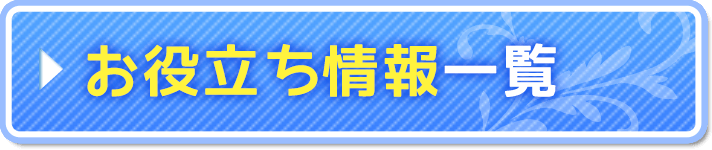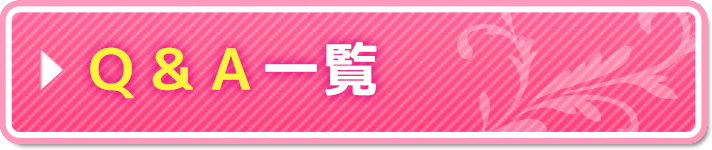障害年金
障害年金を申請する際の手続きの流れ
1 障害年金申請の方法

障害年金は、年金事務所等に、所定の年金請求書に診断書等の資料を添付して提出することによって申請します。
2 初診日と年金の納付状況の確認
障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金の二つがあります。
どちらの年金を請求すべきかは、初診日において国民年金に加入していたのか厚生年金に加入していたかによって決まります。
また、障害年金を請求するためには、年金保険料を一定程度納めていたことも必要になります。
この納付要件についても、初診日を基準時として判断します。
そのため、障害年金を申請するに当たっては、まずは初診日と年金の納付状況を確認することが必要になります。
3 診断書の取得、病歴・就労状況等申立書の作成
初診日や納付要件等に問題がなければ、医師に診断書の作成を依頼します。
障害の程度が、障害年金の支給を受けるに足るものかどうかについては、医師の診断書がもっとも重視されますので、診断書に正確に症状等を記載してもらえるよう、自分の症状等を正確に医師に伝えることが必要になります。
また、これまでの病気の状況や生活状況等についてまとめた病歴・就労状況等申立書を作成します。
4 書類の提出
診断書や病歴・就労状況等申立書、その他の添付資料がそろったら、年金事務所に年金請求書を提出し、障害年金の申請を行います。
申請後、日本年金機構で、障害の状態が障害年金に該当する程度かどうかや、その他の障害年金が認められるための条件に該当するかどうかの審査が行われ、障害年金の支給が認められた場合には、「年金証書」が、支給が認められなかった場合には「不支給決定通知書」が送られることになります。
5 詳しくは専門家にご相談ください
以上が、障害年金申請の大まかな流れになります。
ただ、個別の状況によっては、他に必要な資料を用意したり、障害年金の受給が認められやすくするよう他の資料を添付したりすることもあります。
詳しくは、弁護士、社労士等の専門家にご相談ください。
障害年金申請が不支給になった時の対応について
1 障害年金申請が不支給になった時の対応

障害年金申請をしても、必ず障害年金が受け取れるわけではありません。
審査の結果、不支給となる場合もあります。
では、不支給となった場合、どのように今後の対応をすればよいでしょうか。
2 不支給の理由
障害年金が認められない場合、「国民年金の支給しない理由のお知らせ」等と記載された書面が届きます。
さらに、不支給決定と却下決定に大きく分かれます。
どちらも障害年金の受給が認められないという結果であることは分かるかと思いますが、不支給決定は、厳密には障害の程度が障害年金受給の程度に達していないと判断された場合に出される決定です。
他方、却下決定は。障害の程度を審査する前段階の要件を満たしていないと判断された場合に出されます。
前提として、障害年金は、原則初診日が特定されており、保険料納付の要件を満たしている必要があります。
そのため、初診日が特定できないため、あるいは過去の保険料納付状況から要件を満たしていないと判断された場合には、障害の程度にかかわらず却下となります。
そのほか、提出書類では障害認定日の症状が判断できない等という理由で却下となることもあります。
3 審査請求
不支給を争うにあたってまず考えられるのが、審査請求です。
これは、不支給の判断が誤りであったとして、再度の審査を求める手続きといえます。
申請時の書類だけでなく、追加の書類を提出して再考を求めること等も可能ですが、不支給の結果を知った日から3か月以内に行うという期限がありますので、審査請求を考えている場合には申請期限にご注意ください。
4 再申請
審査請求は、当初の申請を前提に、その判断の再考を求める手続きですが、はじめから審査をやり直すことも可能です。
3か月の期限を過ぎてしまった場合には、審査請求はできないため、再申請するしかありません。
そのほか、症状が悪化した等、従前の申請とは状況が変わっているような場合に、審査請求をあえて行わず、従前の状況からさらに悪化したため現在時点の症状に基づいて改めて申請をするという選択をすることも考えられます。