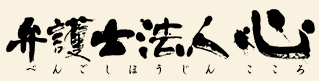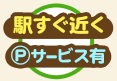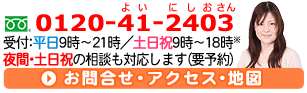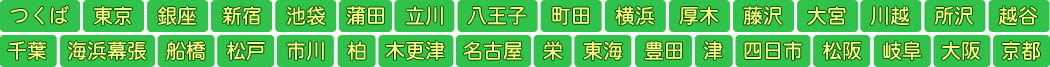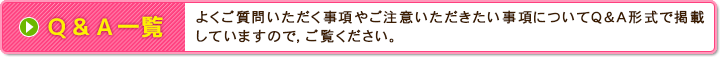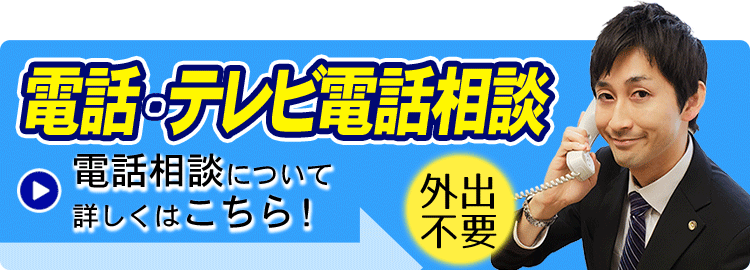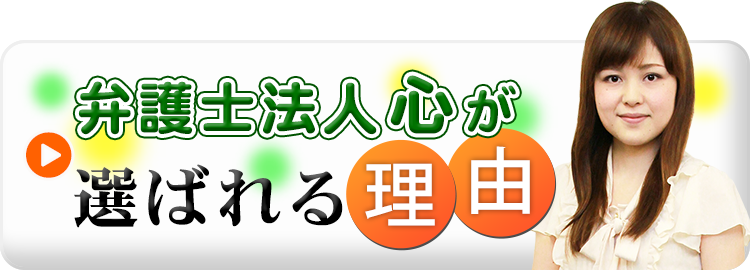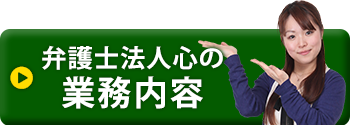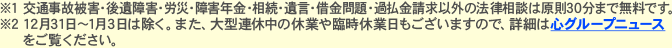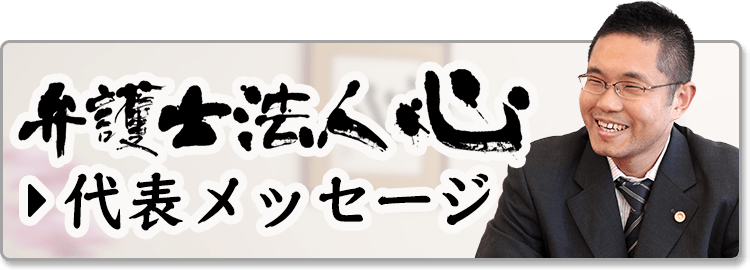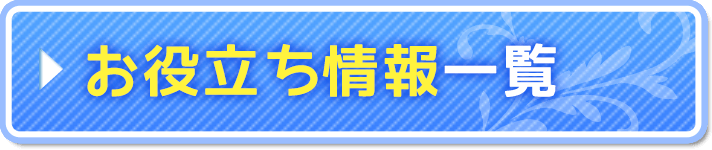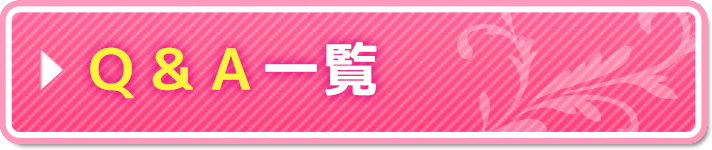相続人の中に認知症の方がいる場合の遺産分割
1 原則として成年後見人が必要となります
相続人の中に、認知症を患われていて物事を判断する能力がない方がいる場合には、その方を成年被後見人として成年後見人を選任する必要があります。
そして、その成年後見人が、認知症を患われている相続人の方を代理して遺産分割協議をすることになります。
成年後見人の方も相続人である場合には、認知症の相続人の方との間に利益相反関係が発生してしまいますので、この場合には成年後見監督人が選任されている場合には成年後見監督人が、そうでない場合には特別代理人の選任が必要となります。
以下、詳しく説明します。
2 成年後見人の選任
成年後見人を選任するためには、家庭裁判所で成年後見人選任申立てという手続きを行わなければなりません。
申立ての際には、成年後見人選任の申立書を作成するほか、認知症の方の診断書(後見相当である旨の意思の診断書)や財産に関する資料も用意する必要があります。
認知症の方に推定相続人がいる場合には、推定相続人全員の同意書が必要となることもあります。
申立てをした後は、家庭裁判所によっては後見人候補者の方に事情の聞き取りなどが行われることもあります。
そして、問題ないと判断されたら、成年後見人が選任されます。
3 成年後見監督人、特別代理人
利益相反が生じる典型的なケースとしては、相続人が認知症を患われている配偶者と子であるというものが挙げられます。
このような場合、被相続人の子が被相続人の配偶者(子から見た親)の成年後見人となると、遺産分割協議においては利益相反の関係となります。
親族が成年後見人になる場合、成年後見監督人(多くの場合、弁護士等の法律の専門家)が選任されることも多いので、成年後見監督人がいる場合には、遺産分割協議の際には成年後見監督人が認知症の相続人の代理人になることができます。
成年後見監督人がいない場合には、家庭裁判所で別途利益相反関係にない方を特別代理人にする手続きをしなければなりません。
そして、特別代理人が認知症の方の代理人となって遺産分割協議を行います。